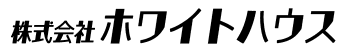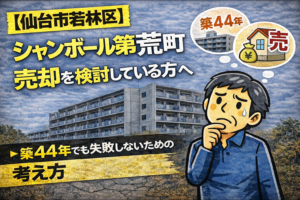仙台市に持ち家をお持ちの方や仙台市に空き家などをお持ちの方で、
売却を考えていらっしゃる方は必見です。
東北地方で唯一の政令指定都市である仙台は、
109万人の人口を擁し、
首都圏からの良好なアクセスもあいまって、
周辺市町村を含めて約150万人の仙台都市圏を形成し、
東北地方の商業の中心となっています。
東北地方の中心都市として発展してきた仙台ですが、
主要な不動産投資エリアの一つとなっています。
仙台市に不動産を持っている方の中には、
どのタイミングで家を売ればいいのかが分からず、
悩んでいる人も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、
仙台の家をいつ売るべきなのか、
人口推移や地価公示価格の推移から、
仙台の不動産の売却タイミングについて考えていきたいと思います。
仙台の不動産の価格推移と適切な売却タイミング
仙台市は、
青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区の
5区で成り立っている政令指定都市です。
政令指定都市とは、
人口50万人以上を有している市で、
都市としての規模や行政能力を備えていると判断された場合に指定されます。
政令指定都市に指定された場合、
県から財源の一部や権利が移譲されるため、
より積極的に行政サービスの拡充を行うことが可能です。
令和6年2月現在、
横浜市、名古屋市、京都市、大阪市といった全国20都市しか
指定されていない中に仙台が含まれているため、
東北地方の重要な拠点であることが分かります。
政令指定都市は人口が多く、
比例して不動産の賃貸需要も期待できるため、
不動産価格の上昇の可能性もあります。
この記事では、
不動産の売却タイミングについて、
以下の3つのポイントを中心に考えて行きたいと思います。
1 仙台の人口推移
2 仙台の地価公示価格推移
3 インバウンドの需要拡大
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
仙台の人口推移
仙台市が公表している「推計人口及び人口動態(令和6年2月1日)」によると、仙台市の各区の人口と世帯数、過去5年の人口推移と世帯数推移は以下の通りです。
各区の人口と世帯数
| 区 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 青葉区 | 31万4,757人 | 16万9,894世帯 |
| 宮城野区 | 19万4,154人 | 9万8,130世帯 |
| 若林区 | 14万2,446人 | 7万1,386世帯 |
| 太白区 | 23万7,257人 | 11万0,439世帯 |
| 泉区 | 20万8,418人 | 9万5,615世帯 |
過去5年の人口・世帯数の推移
| 年 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 109万0,263人 | 52万0,556世帯 |
| 令和2年 | 109万6,704人 | 52万5,455世帯 |
| 令和3年 | 109万7,237人 | 53万1,764世帯 |
| 令和4年 | 109万9,239人 | 53万9,705世帯 |
| 令和5年 | 109万7,814人 | 54万4,894世帯 |
過去5年間の人口推移と世帯数推移を見ると
令和5年に若干数減少しているものの
全体的に増加傾向にあることが分かります。
人口が増加すると不動産の賃貸需要も増える傾向にあります。
人口が増加傾向にあることで仙台市の不動産価格が
上昇する可能性があると言えるでしょう。
仙台の地価公示価格推移
宮城県不動産鑑定士協会が公表している「地価公示(令和5年)」では、
仙台市の住宅地の地価を前年と比較すると、
292地点が上昇、6地点が横ばい、7地点が下落となりました。
宮城県全体と仙台市の住宅地の平均変動率の過去5年の推移を
比較すると以下の通りです。
| 年 | 宮城県 | 仙台市 |
|---|---|---|
| 平成30年 | 2.7% | 4.6% |
| 令和元年 | 3.5% | 5.8% |
| 令和2年 | 3.5% | 5.7% |
| 令和3年 | 1.0% | 2.0% |
| 令和4年 | 2.8% | 4.4% |
| 令和5年 | 4.0% | 5.9% |
宮城県全体の地価も上昇していますが、
仙台市の地価の方が顕著に表れています。
上昇幅は年々大きくなっており、
仙台市は今後さらに地価の上昇が期待できると言えます。
新型コロナウイルスの影響により
マクロ経済に打撃を受けたタイミングであっても
仙台市の地下は上昇し続けました。
地価総平均:32万3,720円/㎡
坪単価:107万0,148円/坪
変動率:+7.43%
※上記の数字は仙台市の公示地価と基準地価の総平均を記載しております。
※参考:土地価格相場がわかる土地代データ
仙台市のエリア別の地価ランキングでは、
1位が青葉区、2位は若林区、3位は宮城野区でした。
仙台市の地価は2013年以降上昇を続けています。
仙台市は高い水準をキープしており、
地価が保たれている今は売却のタイミングとしてもベストと言えるでしょう。
また、
宮城県の発表している「市町村別の土地取引件数」では、
宮城県と仙台市の土地取引件数も10年程前よりも概ね増加傾向にあり、
毎年一定数あることがわかります。
土地取引件数(単位:件)の一覧表
| 県全体 | 仙台市 | 仙台市以外 | |
|---|---|---|---|
| 平成23年 | 20,564 | 8,779 | 11,785 |
| 平成24年 | 25,945 | 11,333 | 14,612 |
| 平成25年 | 37,993 | 12,451 | 25,542 |
| 平成26年 | 41,083 | 12,822 | 28,261 |
| 平成27年 | 33,316 | 12,379 | 20,937 |
| 平成28年 | 32,618 | 13,310 | 19,308 |
| 平成29年 | 31,238 | 13,890 | 17,348 |
| 平成30年 | 31,185 | 15,327 | 15,858 |
| 令和元年 | 28,433 | 13,220 | 15,213 |
| 令和2年 | 27,350 | 13,548 | 13,802 |
| 令和3年 | 28,182 | 14,298 | 13,884 |
| 令和4年 | 26,519 | 13,194 | 13,325 |
土地取引が仙台市や宮城県において盛んに行われていることがわかります。
所有している不動産の地価推移を調べ、
上昇しているかどうか確認してみるのはいかがでしょうか。
仙台市のインバウンドの経済効果
仙台市の公表している「市内外国人宿泊者数統計」によると、
2011年には東日本大震災の影響で宿泊者の数は大幅に減少したものの、
その後は2019年にかけて回復・増加し、
震災前を大きく上回りました。
新型コロナウイルスの影響で2022年までは減少傾向にあるものの、
2023年以降は回復が見込まれ実際に増加しています。
仙台市の外国人宿泊者数の推移
| 年 | 外国人宿泊者数 |
|---|---|
| 2010年 | 9万706人 |
| 2011年 | 2万4,071人 |
| 2012年 | 5万7,297人 |
| 2013年 | 5万5,871人 |
| 2014年 | 6万8,834人 |
| 2015年 | 11万5,947人 |
| 2016年 | 12万8,450人 |
| 2017年 | 16万8,632人 |
| 2018年 | 20万4,340人 |
| 2019年 | 33万4,767人 |
| 2020年 | 7万1,010人 |
| 2021年 | 1万8,306人 |
| 2022年 | 3万4,303人 |
令和5年4月26日より54日間にわたり開催しました
第40回全国都市緑化仙台フェア(未来の杜せんだい2023)では、
目標来場者数100万人を超える約115万人もの来場客があり、
外国人も多く見られました。
仙台市はタイとの関係を深めており、
タイ航空に対して現在運休となっている仙台-バンコク間定期便の一日も
早い再開を要請する等しています。
新型コロナウイルスの収束により、
インバウンド需要は大きく回復している状態にあります。
インバウンドは不動産価格に直接的な影響を与える要因ではありませんが、
インバウンドによる経済効果によって、
周辺地域の再開発、
人口の増加などが期待できます。
2024年は不動産売却に適したタイミング?
仙台市は地価や人口推移、
外国人宿泊者数も上昇傾向にあり、
不動産価格が上昇する可能性があると言えます。
実際に、
10年以上かけて仙台市の地価は上昇し続けています。
また、
不動産価格は金融機関の融資状況や、
物件の状態、
立地によっても上下します。
具体的な例としては、
2009年のリーマンショックや2011年の東日本大震災で大幅な相場下落が続き、
その後2012年以降は上昇傾向に転じました。
こういった価格上昇の背景には、
政府が打ち出す経済政策などへの期待が影響していると考えられます。
また、
人口増が見込まれる地域の価格は上昇傾向、
人口減が進む地域では下降傾向にあることも見逃せません。
このように、
経済政策や大規模なイベント、
人口の増減などさまざまな事柄が不動産価格を動かしています。
従って、
大きな流れを見誤らないように売却時期を計ることが大切です。
ただし、
市況の見極めはプロの投資家や不動産会社でも難しいもの。
そこでまずは
「購入時点よりも相場が上がっていれば売りどき」
と考えるのも一つの方法です。
不動産の売却時はこれらの全体的な仙台市の状況を踏まえたうえで、
個別に判断していくことが大切です。
定期的に不動産の価格を査定しておき、
実際の物件価格がどのように変動しているのか、
築年数や地価はどのような影響を与えているのか確認しておくことが大切です。
株式会社ホワイトハウスでは
無料でお気軽に不動産価格の査定を依頼することが可能です。
まだ売却意思が固まっていない段階でも、
査定だけ受けることが可能です。
もし、
納得できる査定結果が出ているのであれば、
その上で売却を依頼することもできるので、
検討段階からこまめに査定依頼をしておくと良いでしょう。
不動産を売却する時期や季節に違いはあるの?
不動産の売却に時期や季節によって違いはあるのですか?
と聞かれることがあります。
売主様は『売れやすい』タイミングや、
『売れにくい』タイミングがあるのであれば
把握しておきたいと考えるのは当然のことでしょう。
⚫︎3月~4月入居を希望する家族が多い
お家を購入する方で多いのが3月~4月入居を理想とするご家族です。
購入者はお家の購入時期というより、入居時期を重要視する傾向があるのです。
子供が小学校や中学校に入学するタイミングで引っ越したい、
途中で学区などを変えたくないという意見がとても多く聞かれます。
住まいは「生活の場」ですから、
世の中の活動の流れから影響を受けるわけです。
賃貸物件を思い浮かべてみてください。
3月〜4月の住み替えシーズンには、
条件の良い部屋が見つかりにくいですよね。
反対に、
この時期に入居者が決まらなかった部屋は4月を過ぎても空室になりがちです。
これは、
売却についても同じことが言えます。
いくら条件が良い物件でも、
時期を逃すと買い手が見つからなかったり、
希望価格で売れなかったりします。
できるだけ希望通りに住まいを売却したければ、
需要期の少し前から活動しはじめることが大切です。
⚫︎購買意欲の強い購入希望者は常に探している
3月~4月入居を目指してお家探しをしておられるご家族がとても多いのは事実ですが、
実際にその時期に皆さんが購入しているかと言えば、そうでもありません。
賃貸とは違い一生のお買い物ですので、
インターネットが普及し、
情報がいつでも手に入りやすい昨今では、
購入希望者は常に物件を探しています。
「入学や進学のタイミングで新居を買おう」と考えていても、
その時期に理想のお家があるとは限りません。
タイミングを見計らっているうちに
「めぼしい物件がすべて売れてしまった」
という方は少なくないはずです。
本気で購入を考えている方は、
どんな時期でもしっかり新着物件はチェックしますし、
どんな時期でも理想のお家があれば購入するのです。
⚫︎売却したいお家の周辺物件を調べる
お家を売るときは、売却時期や季節を重視するより、
近隣に同じような物件が売りに出ていないか調べることが重要という考え方もあります。
同じような条件の物件が近隣で売り出されている場合は、
購入希望者も、
より良い物件をより安く購入しようと、
価格や条件を比較しますので、
価格競争に陥りがちです。
もし売却するのを急いでいるのならば、
躊躇せず値下げするのも一つかもしれません。
急がずに売却価格を維持したい場合は、
競合が多い時期が過ぎてからじっくりと売れば良いのです。
『売却時期を考える』より、
『周りに競合物件がないタイミングでお家を売る』
という考え方です。
⚫︎税制的にお家を所有している期間も重要
不動産を売却した際の譲渡所得には、譲渡所得税が課されます。
この譲渡所得税は、
「所有期間5年」を境に区別されることをご存じでしょうか。
所有期間5年未満での売却を「短期譲渡所得」、
5年超では「長期譲渡所得」と呼び、
以下のように税率が変わるのです。
・短期譲渡所得(所有期間5年以下)……39.63%(内訳:所得税30.63%、住民税9%)
・長期譲渡所得(所有期間5年超)……20.315%(内訳:所得税15.315%、住民税5%)
また、
居住用の場合に限り、
以下のような軽減税率が適用されます。
・保有期間10年超(譲渡所得6,000万円以下の部分)……14.21%(内訳:所得税10.21%、住民税4%)
・保有期間10年超(譲渡所得6,000万円超の部分)……20.315%(内訳:所得税15.315%、住民税5%)
購入してから5回目もしくは10回目の元日を迎えたタイミングで、
税金が安くなることを覚えておきましょう。
住まいの売却では、
こういった税率変更の節目も意識すると良いでしょう。
⚫︎お家の築年数にも注意
基本的には、
築年数が短いほど売却価格で高値が付き、
長くなるごとに安くなる傾向があります。
しかし、
価格下落は一定ではないのです。
ここで意識したいのが「築15年」と「築20年」という数字。
中古マンションの販売価格は、
おおむね築15年までの下落幅が大きく、
その後はゆるやかに安くなります。
同じように一戸建ては築20年までは大きく価格が下落し、
それ以降はほぼ横ばいです。
どちらも価格の下げ止まりが起こる築年数がそのあたりとなっています。
マンションは、
経年劣化への対応と資産価値の維持という目的で、
建物全体の「大規模修繕」を必ず行います。
これの第一回目の実施めどが、
大体築15年目なのです。
新築時点でピークだった価値が、
人が住み、
経年劣化で下がり続けますが、
一旦15年目の大規模修繕で持ち直して以降、
下げ幅がゆるやかになるということが推察できます。
一方、
一戸建ては木造建築がほとんどで、
日本では「築20年で一戸建ての建物は無価値」
という考えが広く浸透していました。
しかし、
今や「良質な住宅ストックの形成」に向け、
国がさまざまな方策で取り組んでいる中、
築20年で査定価格0(ゼロ)という認識はなくなりつつあります。
とはいえ、
木造住宅の法定耐用年数は22年ということを鑑みると、
新築からの価値の下落はおおむね20年で止まるという一定の線引きは、
妥当かと思われます。
売主としては、
価格が落ちきってしまう前、
つまり築15年や築20年以前のできるだけ早い段階で売却を意識すべきでしょう。
あとは、
どれだけ劣化しにくい構造や素材で建てられているか、
適正な修繕が施されているか、
需要が高いエリアにあるか、
売却時にリフォームやリノベーションを施工できるかといった
物件ごとの状況で大分違ってくるということも認識する必要があるでしょう。
まとめ
仙台市は、
宮城県の面積の10%程度しかないにもかかわらず、
人口100万人を超える東北地方唯一の政令指定都市です。
人口増加、
好調なインバウンドの需要拡大、
再開発への注力などの影響を受けて、
仙台市の土地は右肩上がりに上昇しており、
特に最近の伸び幅が大きいため、
不動産価格の上昇の可能性があるエリアと言えます。
しかし、
リーマン・ショックのような景気低迷が生じた場合、
日本全体の経済悪化によって地価が大幅に下落する可能性があるので注意が必要です。
また、
不動産価格は全体の数値データを踏まえたうえで、
最終的には個別の物件ごとに価格の傾向を確認しておくことも大切です。
こまめに査定を受けておき、
売却のタイミングは慎重に検討すると良いでしょう。
お客様の状況や所有している物件の内容も異なりますので、
詳細を知りたいという方はお気軽に株式会社ホワイトハウスまでお問い合わせください。