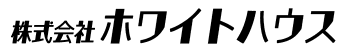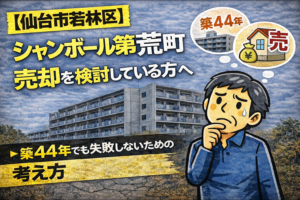高齢化が進む日本では、相続や資産整理を目的として不動産売却を検討するご家庭が増えています。
しかし、いざ売却を進めようとしたとき、不動産の所有者が認知症だった…というケースは決して珍しくありません。
今回は、不動産所有者が認知症になった場合に不動産売却はできるのか?
また、売却を進めるためにはどうすればよいのか?
注意点や対処法について、わかりやすく解説します。
不動産所有者が認知症の場合、売却できるの?
結論から言うと、原則として「認知症の方ご本人による売却はできません」。
なぜなら、不動産の売買契約は「法律行為」に該当し、本人の判断能力(意思能力)があることが大前提となるからです。
意思能力とは、自分が何をしているのかを理解し、その結果を予測し判断できる力のことを指します。
認知症の症状が進行している場合、この判断能力が欠けていると見なされ、たとえ売買契約を結んでも「無効」とされてしまうリスクがあります。
こんなケースは要注意!
- 不動産の所有者が80代以上で、記憶があいまいな様子
- 金銭の管理が難しくなり、通帳や印鑑の管理も困難
- 会話の中で日時や人の名前を間違えることが多くなってきた
こうした場合、ご本人の意思確認がスムーズに取れない可能性があり、売却手続きに入る前に法的な準備が必要となります。
対処法①:成年後見制度を利用する
認知症の方の不動産を売却するために最も代表的な方法が、「成年後見制度」の利用です。
成年後見制度とは?
認知症などで判断能力が低下した人を保護・支援するために、家庭裁判所が選任した「成年後見人」が、代わりに法律行為を行える制度です。
成年後見人は、本人の財産を管理したり、不動産売買の契約を代行したりできます。
手続きの流れ
- 家庭裁判所へ申立て(親族または市町村長が行う)
- 医師による診断書を提出
- 裁判所による審査
- 成年後見人の選任(約2〜6ヶ月程度)
注意点
- 不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要です。
- 売却の理由が「本人の利益のため」でなければなりません(例:施設費用の支払い、空き家の維持が困難など)。
- 成年後見制度には費用もかかり、選任された司法書士や弁護士が後見人になる場合、年間数万円〜数十万円の報酬が発生します。
対処法②:認知症が軽度なら医師の診断を受ける
認知症と診断されても、まだ軽度な段階で意思能力が残っていることもあります。
この場合、医師による「意思能力あり」の診断書を得られれば、本人の意思で売却手続きを進めることが可能です。
ただし、診断の結果によっては手続きがストップする可能性もあるため、早めの確認が重要です。
対処法③:家族信託(民事信託)という選択肢も
近年注目されているのが、「家族信託」という制度です。
これは、将来的に本人が判断能力を失っても、信託契約によって信頼できる家族が不動産を管理・売却できるようにしておく仕組みです。
例えば、
- 親が「長男にこの家を託す」と信託契約を結ぶ
- 長男が将来、親の代わりに売却や管理を行える
といった形です。
ただし、家族信託は契約時に本人の意思能力があることが前提となります。
すでに認知症が進行していると、利用はできません。将来を見据えて、早めに準備しておくことがカギとなります。
売却を急ぐなら、専門家に相談を
認知症の方の不動産売却は、法的・実務的なハードルが非常に高いため、自己判断で動かず、以下のような専門家へ早めに相談することをおすすめします。
- 司法書士:成年後見申立て手続きのプロ
- 弁護士:複雑な相続・共有名義問題に対応
- 不動産会社(売却専門):売却の進め方や注意点のアドバイス
当社でも、認知症のご家族が所有する不動産売却のご相談を数多く承っております。
司法書士・弁護士とも連携し、ワンストップで対応可能です。
まとめ
✅ 不動産所有者が認知症の場合、本人の判断能力がなければ売却は不可
✅ 成年後見制度を利用すれば、後見人が売却を代行できる
✅ 医師の診断によっては、本人が売却可能なケースも
✅ 事前に家族信託を活用しておけば、スムーズな売却も可能
✅ 迷ったら、不動産会社や司法書士へ早めに相談を!
認知症と不動産売却は、時間との勝負です。
判断能力があるうちに準備を進めることが、将来の家族間トラブルや損失を防ぐ最大の対策となります。
「うちは大丈夫」と思わずに、ぜひ早めにご相談ください。
私たちホワイトハウスでもご相談をお受けしております。