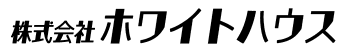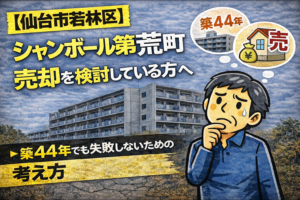結論:売却自体は可能。ただし、告知・事前調査・コスト見積りを外すと“契約不適合責任”や工事ストップのリスクが高い。
アスベスト(石綿)を含む可能性がある建物でも、法律上、売却そのものは禁じられていません。
しかし、2021~2023年にかけて改正・強化された各種規制により、解体・改修前の「事前調査」や報告・有資格者の関与が義務化され、対応を誤ると高額な是正費用や罰則につながります。
売主がアスベストの存在を把握していながら告げなかった場合、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を問われ、損害賠償や解除に発展する可能性もあります。
まずは「売れる/売れない」よりも、どう開示し、どうコストとスケジュールを管理するか”が肝です。
1. そもそも、いつの建物が危ない?――2006年以前着工は要注意
日本では、健康被害の深刻化を受けて段階的に使用禁止が進み、2006年の法改正で原則全面禁止になりました(既存建物に組み込まれている分の使用継続は可)。
したがって、2006年(平成18年)頃までに建築・着工した建物は、含有リスクが相対的に高いと理解しておきましょう。
とはいえ、“築年数だけで含有の有無は断定できない”ため、売却前に専門家による事前調査で事実を押さえることが不可欠です。
2. 法規制のいま:2021~2023年の改正で「事前調査の方法と資格者」が明確化・義務化
- 大気汚染防止法改正(公布:2020年、施行:原則2021年4月~)
すべての石綿含有建材を規制対象に拡大し、“解体・改修工事の事前調査”を法定化、一定規模以上では調査結果の自治体等への報告を義務化しました。違反に対する直接罰も新設されています。 - 2022年4月~:電子報告制度スタート
規模に関係なく、解体・改修前は必ずアスベスト使用の有無を調べる義務があり、一定規模以上では労基署・自治体への報告が必要になりました。 - 2023年10月~:有資格者による調査が義務化
事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」など“必要な知識を有する者”が実施しなければなりません。素人判断や不十分な調査は通用しない時代です。
ポイント:売主が解体せず“現状のまま”売却する場合でも、買主が解体・改修を予定していれば、こうした規制コストを強く意識するため、価格交渉材料になることを理解しておきましょう。
3. 売主が負うリスク:「知っていて告げなかった」=契約不適合責任の可能性
売買後にアスベストが判明すると、撤去費用や工期延長分、代替住居費用などの損害賠償・契約解除が争点になり得ます。
特に、売主が存在(または可能性)を認識していたのに告知しなかった場合、責任追及を受けるリスクが高まります。
“疑い”段階でも、把握している事実・調査履歴を開示して買主と情報を共有する姿勢が不可欠です。
4. 売却前にやるべき“5つの実務対策”
① 事前調査(書面・目視・分析)を有資格者に依頼
2006年以前の建物や用途・仕様によっては、吹付材や保温材、成形板、仕上塗材など多様な箇所に含まれている可能性があります。
書面+目視+分析という法定手順で有資格者が調査し、調査報告書を作って保管・共有しましょう。
② 結果を“ありのまま”開示(重要事項説明・告知書)
宅建業法35条の法定説明事項に直接列挙はないものの、買主の判断に重要な影響を与える事実として、実務上は詳細な説明が不可欠です。
隠すほど後のコストは増大します。
③ 解体・改修が前提なら「想定コスト」を見積もり、価格に反映
アスベスト除去・封じ込め等の工事費用は高額化しがちで、工期の遅延リスクもあります。
見積り(幅を持たせたレンジ)を添えて売り出すことで、買主の不安を先に“数値化”し、無用な値引き交渉を避けられます。
④ 「現状有姿」売買+契約不適合責任の範囲/期間を明確化
“現状のまま売る”という特約を設ける場合でも、事前に把握した事実は開示が大前提。
その上で、契約不適合責任の期間・範囲を合理的に限定する条項を弁護士や宅建業者と詰めておくと安心です。
⑤ 買取(不動産会社が買主)という選択肢も検討
スピード優先・責任回避を重視するなら、宅建業者による買取も選択肢です。
価格は相場の7~8割に落ちるのが一般的ですが、告知・工事対応・契約不適合責任の負担を大幅に軽減できます。
アスベストを理由に仲介で長期化するより「早く終える」戦略が合うケースもあります。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 「アスベストがある=売れない」ですか?
売れます。 ただし、調査・告知・コスト把握を省くと、あとで“売れたけれど揉める”という最悪の展開になります。
スムーズに売るほど、先に開示しておくのが王道です。
Q2. 既存住宅売買瑕疵保険でカバーできますか?
既存住宅売買瑕疵保険は、基本的に「構造耐力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」などに限定されており、アスベストそのものの除去費用は対象外となることが多いのが実務です(商品ごとに補償範囲は異なるため、必ず約款を確認してください)。
Q3. 調査は誰でもできますか?
できません。 2023年10月以降、有資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査が義務化されています。
6. 売却フローに落とし込む「実務チェックリスト」
- 築年数・工法・改修歴を整理(2006年以前着工は特に要注意)。
- 有資格者へ事前調査を依頼(書面・目視・分析)。
- 調査報告書を保管し、買主へ開示(重要事項説明・告知書で明記)。
- 解体・改修を想定するなら、除去費・工期のレンジ見積りを提示。
- 契約不適合責任の範囲・期間・現状有姿特約を弁護士等と設計。
- 仲介で長期化・対立が見込まれる場合は、買取スキームも比較。
- (買主側の)工事段階では、報告義務や作業基準・罰則を理解した事業者を手配。
まとめ:“売却できるかどうか”より、“どう安全に・透明に進めるか”が勝負
- アスベスト含有の可能性がある物件でも売却は可能。
- ただし、2021~2023年の規制強化で、“調査の質”と“開示の正確性”が以前にも増して重要になりました。
- 告知を怠れば契約不適合責任のリスク、工事段階での違反は罰則や工期遅延の直撃。
- 有資格者の事前調査→報告書開示→コスト見積り→合理的な契約設計という王道プロセスを踏めば、トラブルを大幅に減らし、価格交渉の材料も“見える化”できます。
不安があれば、アスベスト調査者・宅建士・弁護士(契約条項)・工事業者を一つのチームにして、「最終手取り」「工事費のレンジ」「スケジュール」を同じ表に並べるところから始めましょう。可視化こそ最大の防御策です。
✅ アスベストの疑いがある場合は当社へご相談を!【無料相談】
📍 経験豊富なスタッフが、
あなたの不安と希望に最大限お応えします!
✅ 無料現地調査
✅ 造成アドバイス・測量士紹介可能
✅ 相続相談もワンストップ対応
📞 お電話でのお問い合わせはこちら
【フリーダイヤル】0120-130-082(営業時間:9:00〜17:00/年中無休)