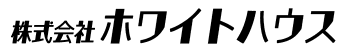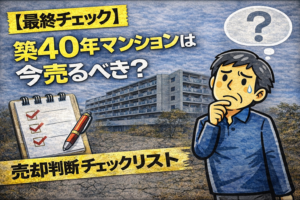全国で増え続ける空き家は、深刻な社会問題になっています。
実は空き家には、目的ごとに4つの種類があることをご存じですか?
今回は空き家の種類についてご紹介し、
増加率が高い種類や空き家を放置するリスクについて解説します。
空き家の現状
空き家とは、文字どおり誰も住んでいない家のことです。
メンテナンスを怠ったために、建物の状態が悪化している中古物件なども少なくありません。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されたこともあり、
空き家を放置しておくことが難しくなりました。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、
空き家の数は848万9,000戸と過去最高となり、
全国の住宅の13.6%を占めています。
空き家については、少子高齢化の進展や人口移動の変化などを背景に、
増加の一途をたどっており、管理が行き届いていない空き家が、
防災、衛生、景観等の面で人々の生活環境に影響を及ぼすという社会問題が起きています。
また、少子高齢化が進展する中、空き家の有効的な利用のための対応が各地において必要とされています。
空き家が増加する背景
少子高齢化
厚生労働省が発表した人口動態統計によると、
出生数は減少傾向が続いており、2022年には合計特殊出生率が過去最低を記録しました。
今後も少子高齢化が進むと予想されます。
子どもの数が減ることで、親が亡くなった後の実家が空き家として残される状況も増えています。
これが空き家増加の主な理由の一つです。
核家族化と新築住宅の需要
かつては結婚後に親と同居するケースが一般的でした。
しかし、昨今は核家族化が進み、世帯数が増えています。
また、家を持ちたい方は新築住宅を好む傾向が強いです。
中古住宅を再利用せずに新築住宅を求める世帯が増えるほど、
空き家も増加していくと考えられます。
税金面
固定資産税は不動産の種類によって税率が異なります。
建物があると住宅用地とみなされ、住宅用地の課税標準の特例が適用されて税率が下がります。
一方、更地にすると解体費用がかかり、税率が上がります。
このことから、税金対策として放置しているケースも少なくありません。
都心部への一極集中
仕事や学業の機会を求めて、人々が都心部に移住する傾向があります。
その結果、郊外や地方の住宅が空き家となるケースが増えています。
地震等の自然災害
東北地方は地震や津波のリスクが高い地域です。
仙台市も、2011年の東日本大震災で大きな被害を受けました。
このような自然災害が発生すると、被災した住宅が放置されたまま空き家となることがあります。
相続問題
相続によって空き家を引き継ぐケースが多く、
相続税の負担や管理費用、手間を考慮すると、
空き家を放置することが珍しくありません。
また、相続人が複数いる場合、空き家の処分や活用について合意が得られず、
結果として空き家が放置されることもあります。
これらの背景を踏まえて、仙台市では空き家問題の解決に向けた取り組みが進められています。
空き家バンク制度の活用や、補助金・助成金を用いた空き家の改修・解体、空き家の活用策を提案する相談窓口の設置などが行われており、市民や不動産オーナーに対する支援が充実しています。
空き家の種類
空き家を目的ごとに分類したのが、以下の4種類です。
1. 賃貸用住宅
2. 売却用住宅
3. 二次的住宅
4. その他住宅
ここからは、4種類の空き家の特徴について解説します。
賃貸用住宅とは
賃貸用住宅とは、だれかに賃貸する目的があるが空き家になった住宅です。
現状は入居者がおらず空き家になっていて、新しい入居者を探している状態になります。
中古住宅をイメージするかもしれませんが、新築住宅も含まれます。
新築住宅の場合、最初の入居者を募集している状態です。
賃貸用住宅は4種類の空き家のなかで、もっとも高い割合を占めています。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、賃貸用住宅の割合は空き家全体の51.0%で半数以上です。
売却用住宅とは
売却用住宅とは、だれかに売却する目的で空き家になっている住宅です。
所有者は別のところに住み、空き家を買ってくれる買主を探しています。
売却用住宅も賃貸用住宅と同様、中古住宅・新築住宅の2種類が存在します。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、売却用住宅の割合は少なめで全空き家の3.5%です。
二次的住宅とは
二次的住宅とは、いつもは人が住んでいない住宅のことです。
毎日住んでいる家とは別に、週末や休暇など限られた期間だけ滞在する目的で使われています。
別荘やセカンドハウスなどをイメージしていただくと、わかりやすいのではないでしょうか。
二次的住宅は全種類のなかで割合が低く、総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、空き家全体の4.5%です。
その他住宅とは
その他住宅とは賃貸用住宅、売却用住宅、二次的住宅以外の空き家のことです。
何らかの原因で長い間居住世帯が不在の状態になっている住宅は、その他住宅に分類されます。
建て替えするために解体する予定の住宅も、その他住宅です。
どの種類に分類するか判断に悩む場合は、その他住宅であることが多いでしょう。
その他住宅は空き家全体の41.1%を占め、賃貸用住宅に次ぐ2番目に高い割合となっています。
増加率が高い空き家の種類とは
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によれば、
空き家の総数は1998年から2018年の20年間で1.5倍に増加しています。
ここからは、空き家全体のうち、もっとも増加率が高いのはどの種類になるのか解説します。
増加率1位は「その他住宅」
空き家を種類別に分けたときに、とくに増加ペースが速い種類が「その他住宅」です。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」のデータをもとに、その他住宅の推移を見ていきましょう。
1988年から1998年の10年間では1.39倍増加しています。
次の1998年から2008年の10年間では、増加率1.47倍です。
そして直近10年の2008年から2018年では、1.3倍の増加率となっています。
2013年から2018年の5年間だけで31万戸増加していて、増加のペースが速いです。
持ち家ストックに占めるその他住宅の割合についても2008年から2018年の10年間で1.7%上昇しています。
全住宅ストックに占めるその他住宅の空き家率の全国平均は5.6%です。
高知県、鹿児島県、和歌山県ではその他住宅の空き家率が10%を超えていて、その他住宅の増加が問題となっています。
その他住宅の空き家が増えている一因は、相続した子どもが空き家を管理しきれていないことです。
親から郊外の家を相続しても、子どもは都心で働いていて空き家を放置してしまうケースは少なくありません。
空き家をどう活用するか考えている間に月日が経ち、その他住宅の空き家がどんどん増え続けてしまうのです。
賃貸用住宅は微増
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、ここ10年の賃貸用住宅は微増傾向です。
2008年は412万戸、2013年は429万戸、2018年は432万戸で少しずつ増えていますが、ほぼ横ばいといえるでしょう。
売却用住宅と二次的住宅は減少
売却用住宅と二次的住宅は減少傾向です。
売却用住宅は2008年34万戸、2013年30万戸、2018年29万戸と減ってきています。
二次的住宅は2008年と2013年412万戸で、2018年は38万戸に減少しました。
空き家の種類「その他住宅」を放置するとどうなる?
近年は空き家の増加が社会問題になっているため、空き家放置に対する取り締まりが厳しくなってきました。
空き家を放置するのは所有者に多くのデメリットがあるため、おすすめしません。
とくに目的が決まっていない「その他住宅」を放置すると厄介です。
ここからは「その他住宅」を放置するとどうなるのかについて解説します。
特定空家に指定される
放置された空き家は「空き家対策特別措置法」に基づき、
条件に一つでも該当すると、自治体から特定空家に指定されるおそれがあります。
特定空家とは、そのまま放置すると保安上危険、衛生上有害であると判断された空き家です。
特定空家に指定されると、段階に応じて罰則が科されます。
特定空家に指定された後、自治体からの勧告を受けると、住宅用地の特例措置が受けられません。
住宅用地の特例措置とは固定資産税の課税標準額が最大6分の1軽減される措置です。
これまで受けられていた住宅用地の特例措置が対象外となると、税金の負担が大幅に増えてしまいます。
勧告後も改善が見られない場合は、さらに自治体から命令を受けることになります。
命令に応じない場合は、最大50万円の過料がかかるため注意が必要です。
特定空き家に指定されると行政代執行により、家屋が解体されるケースがあります。
取り壊しにかかる費用は通常よりも高額な場合が多く、その費用は空き家所有者に請求されます。
費用を支払わなければ空き家だけでなく、現在居住している自宅や自家用車なども差し押さえられてしまうのです。
周囲に迷惑がかかる
その他住宅を放置していると、周囲に住んでいる方々にも迷惑がかかります。
放置された空き家は管理が不十分となりやすく、建物が老朽化しやすいです。
建物が破損したり塀が倒れたりした場合、ほかの方に危害を及ぼす可能性もあるでしょう。
管理不十分な空き家があると景観も悪くなるため、不法投棄や犯罪の温床となりかねません。
空き家の敷地内にゴミを放置していれば異臭や害虫、害獣の発生も懸念されます。
空き家は不審者に狙われやすく、住み着かれたり放火されたりするリスクがあります。
空き家が原因で発生した事故の責任は所有者が負います。
このことは民法によって定められており、
たとえば家や塀が壊れて事故が起きた場合、所有者の責任が問われてしまいます。
日頃の管理を怠っていると、建物の老朽化により事故が発生する可能性もあるので注意しましょう。
売却しにくくなる
その他住宅の空き家は適切に管理しないと、建物が速いスピードで老朽化していきます。
建物の老朽化が激しいと、売却しようと思っても買い手がつきません。
売るに売れない状況が続き、放置せざるを得ないという悪循環に陥ってしまいます。
空き家を放置せずに、すぐに売却や賃貸など活用していくことが重要です。
空き家は放置することにメリットはありません。
空き家の管理について
人が住まない空き家は、放置していると老朽化が早く進みやすいものです。
また、放置されているように見える空き家は人の目がないと判断されるため、
不法侵入や放火などの犯罪に巻き込まれてしまうリスクも考えられます。
そのような事態を防ぐために、しっかりとした管理が必要なのです。
空き家の管理には、以下のような内容があります。
換気や通水をする
掃除する
空き家の状態を確認する
換気は、湿気を防止するために大切な作業です。
湿気がこもると、シロアリやカビが発生しやすくなるため、定期的に換気しましょう。
通水は、下水管からのにおいを防ぐためにおこないます。
排水口の下には汚臭の逆流を防ぐための水がたまっていますが、時間が経つとこの水が蒸発してしまうため、水を流す必要があります。
空き家の水道を止めている場合は、ペットボトルなどに水を入れて持参しましょう。
そして、空き家でも掃除が必要です。
とくに庭がある場合は、樹木や草が茂っていると一目で空き家だとわかってしまうため、
防犯面強化のためにも定期的にメンテナンスしましょう。
さらに、空き家の状態にも気を配る必要があります。
たとえば雨漏りがあると、その場所からカビが発生したり腐ったりするかもしれません。
ですから外壁や雨どいの状態、室内のシミの有無などをしっかりとチェックしておきましょう。
空き家を管理する手段
空き家に管理が必要なことはわかったものの、
自分での管理が難しい場合もあるでしょう。
その際は、空き家の管理を請け負っている管理会社に委託すると、
上記の内容を定期的におこなってもらえます。
とくに遠方に住んでいる場合、
管理のために行く時間が取れないなど、
きちんとした管理が困難なこともあるでしょう。
管理会社はそのような際に便利ですし、
地震や台風などによる被害を早めに確認してもらえるなどのメリットもあります。
費用も発生するので、その点も踏まえながら管理方法を考えましょう。